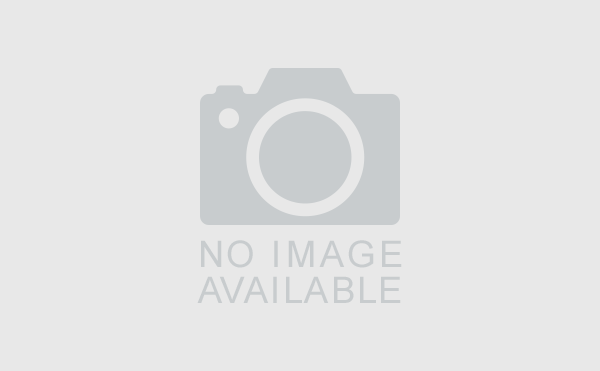工学部 建築学科
こんにちは!工学部建築学科新3回生の森本耀介です。本記事では、建築学科1回生の前期後期の時間割や専門科目、特に難しい授業についてを簡単に話せたらいいな~と思ってます。
はじめに、1回生前期の時間割を見ていきましょう。

赤枠で囲ってるところはデフォルトで入ってる授業、黒っぽいマスは専門科目の授業
これを見て分かるとおり、30単位中(第2外国語も含めると)既に26単位が埋まってしまってるんですよね〜。なので授業の自由度はあんまりない分、他の建築の人と共通の授業が多いので連携はしやすく何だかんだ単位取りやすかったりはします。それでも個人的に難しいと感じた授業はあって、それは、日本都市史と物理学基礎論Aの2つです。日本都市史の難しさは、その成績が期末試験のみで決定してしまうため、授業中にしっかりと板書や先生の話をメモしておかないと詰んでしまうところです。また、物理学基礎論Aでは、微分方程式という概念が突然出てきて当たり前のように使われ出すので内容についていくのに必死でした。あとは前期の専門科目についてですが、日本都市史は先述したとおりなので、月曜の枠に2個並んでいる建築造形実習について簡単に説明します。この授業では、建物の設計図を製図したり、パソコンを活用して3Dモデルを生成したりします。正直めちゃくちゃ楽しい授業で、課題さえ出していれば単位は来るいわゆる「楽単」です。ただ、実習で用いる道具や材料は基本的に自己負担になるので、そこだけ注意しましょう~。
次に、1回生後期の時間割を見ていきましょう。

緑枠で囲ってるところは元々「物理学実験」という授業がデフォルトで入っていた場所
後期も前期と同じくデフォルトで26単位入ってます。物理学実験は、正直この授業を建築の人が取ると専門科目との両立が忙しく、それに見合ったリターンも特にないので切っていいです。後期で最も注意してほしいのは、線形代数と世界建築史です。線形代数は前期と比にならないほど抽象的な内容になり、難しくなります。前期の余裕さで油断した結果散った友をたくさん見てきたので、復習含めちゃんと勉強しましょう。世界建築史は前期の日本都市史と同様成績は記述試験のみで、板書と教科書に加え、先生の話を細かくメモしなければ詰みます。授業プリントや教科書の写真から出題されるので、写真を見て建築の名前や場所、種類、各構造の特徴の説明を書き出せるようにしておきましょう。続いて後期の専門科目について。まず世界建築史は上記の通りです。続いて建築工学概論は、構造や材料等、分野が多岐に渡っているので資料の情報量が多く大変です。設計演習基礎については、前期の建築造形実習の内容に加えて実際に立体模型を作るようになるので、前期よりも製作にかける時間が増えるぐらいに思っておいてください。
1回生の前期後期通して注意してほしいのは、1回生の間に、余ったコマで人社を4単位以上は取っておくことです。基本的に専門に関係ない人社や自然群を、専門科目が本格的に始まる3回生以降に持ち越すのは本当に危険できつい思いをするので、少しでも貯金を作って2回生後期で全て取りきれるよう頑張りましょう。
単位を取る上で大切なことは、友達や先生を頼ること(友達に頼りまくるときはちゃんと奢ったりしよう!)と、人社などはなるべく出席やレポート課題の点数割合が大きい授業を選ぶことです!授業の楽単度合いが分かる「京大楽単bot」や、定期試験の過去問が集約されている「京大wiki」などの便利なツールも検索すればあるので是非活用してください。以上、建築1回生の授業の説明でした~。